丸亀城は、香川県丸亀市にあり、JR予讃線、丸亀駅から南へ約1km、歩いて12分ほどの距離にあり、高松空港からも約30km、一般道で40分ほどとアクセスも良い。
高松駅からの直通電車もあり、高松駅から丸亀駅まで30分、車でも1時間かからないのでセットでも十分観光可能な場所である。
現存天守12城の一つで、日本100名城に選定されている。
丸亀城は、標高66メートルの亀山を利用し、その周りを内堀で囲む平山城で、その石垣は、独特の反りを持たせる「扇の勾配」と呼ばれ、山麓から山頂まで4重に重ねられており、その高さの合計は60メートルで、総高としては日本一高い。

現存天守は1660年完成といわれ、現存天守の中で一番古く、最も小規模だそうで、天守のほか、大手一の門、大手二の門、藩主玄関先御門、番所、御籠部屋、長屋が現存している。
ちなみに大手門と天守の両方が現存しているのは、他に弘前城と高知城のみ。
現在は亀山公園として整備され、園内には丸亀市立資料館がある。
丸亀城の歴史
丸亀城は、豊臣政権時代の1597年、生駒親正(いこまちかまさ)が讃岐17万石を拝領、高松城を本城とし、亀山に支城を築いたのが始まりで、1602年に現在の城郭の大部分が完成している。
1658年に京極高和(きょうごくたかかず)が入封、以後、明治まで京極氏の居城となり、1660年に当時搦手門(からめてもん)を大手門に変更し、その大手門から見上げる石垣の端に現在の天守が完成した。
1919(大正8)年、丸亀市が山上部を借り上げ、亀山公園として開設。
1943(昭和18)年に天守が旧国宝に指定されたが、1950(昭和25)年に、重要文化財となり、2006(平成18)年、日本100名城(78番)に選定される。
2018(平成30)年10月、7月の豪雨や、9月末の台風24号の影響により、帯曲輪石垣と三の丸坤(ひつじさる)櫓跡石垣の一部が崩落した。
復旧工事は当初、2024年3月末完了を見込んでいたが、地中から基礎の役割を果たしていた新たな石垣が見つかり、積み直す石が想定の2倍程度となったため、工期を延長し、2028年3月完了予定だそう。
丸亀城をリア攻め
丸亀城を攻略したのは、2023年6月7日水曜日。
今回の城巡りの旅は、徳島県、香川県の日本100名城及び続日本100名城の計6城と、兵庫県の明石城、洲本城を攻略するためで、メインはもちろん丸亀城。
丸亀城を攻略するには、JR丸亀駅からタクシーまたは徒歩(約1km)、もしくは西側、市立資料館の奥にある駐車場を利用するのが便利

駐車場は無料、平日にも関わらず朝から結構車が停まっていて、ナンバーを見るとほぼ地元ナンバー。
市立博物館の脇を抜け、天守を目指す。

番所、長屋の前を通って大手門へ。

大手門の外から場内を見る。奥には天守の姿がとらえられる。

観光案内所の前を通って、時計回りに登っていく。右手に立派な石垣を見ながら、舗装された坂道を登っていくと、

右側奥に天守の姿が見える。

本当に小さい。

入口で入場料、大人200円を払って中に入る。土足厳禁。
天守閣の観覧時間は9時から16時30分まで。
急な階段を登って、


大手門方面を眺めると瀬戸内海が一望できる。

天守の反対側に回って見上げてみる。

そのまま、時計回りに歩いて、搦手門方面に向かっていく。
確かに以前は搦手門側が大手門だったと言われて納得できるような雰囲気がある。

正面が搦手門からの出入口。

更に時計回りに回っていくと右側が石垣の崩落場所になっている。

石垣が並べられている広い敷地は以前野球場だった場所。

かつてはプロ野球の公式戦も行われたことがあるようだが、丸亀市民球場の開設に伴って、2016(平成28)年4月に閉鎖されたそう。まだ観客席が残ったままになっている。

そのまま先に進むと駐車場に戻ってこられるようになっている。
スタンプと御城印
ちなみに、日本100名城のスタンプは天守閣の中で、窓口のおじさんにお願いすると出してもらうシステムになっている。

御城印も同じ場所で販売しており、2種類とも300円。
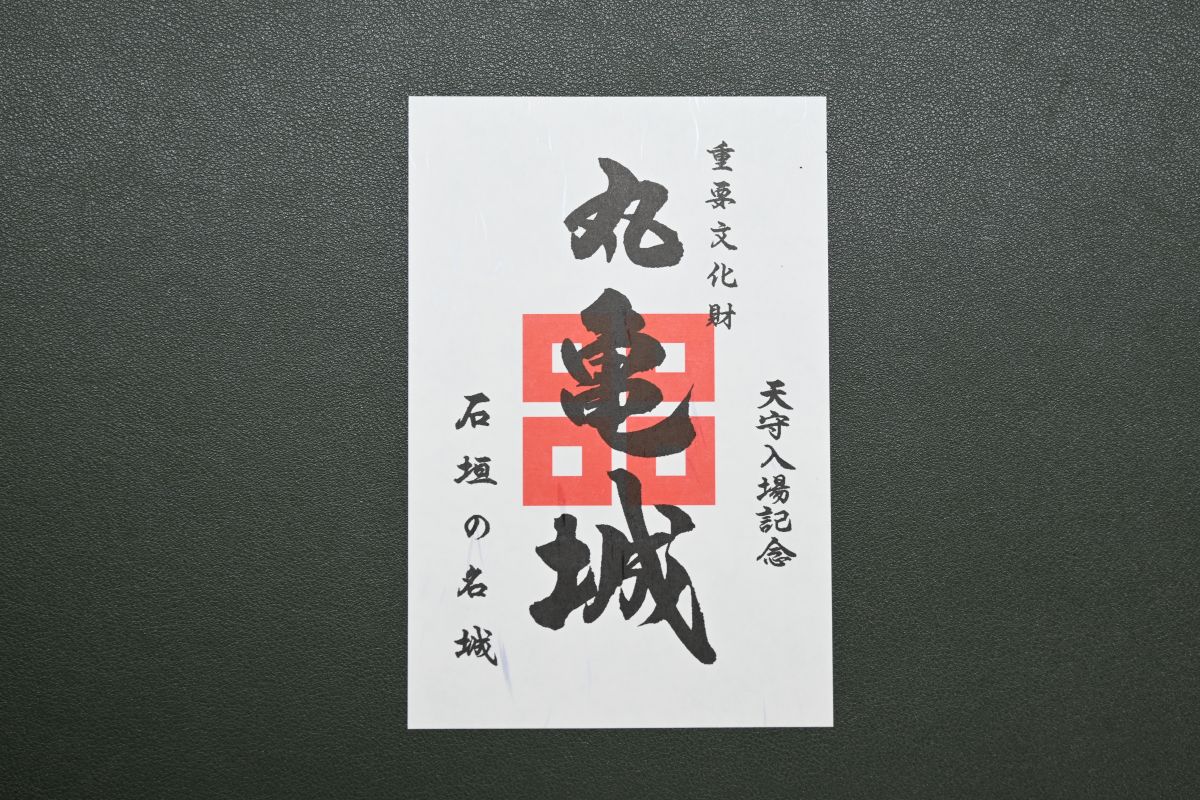
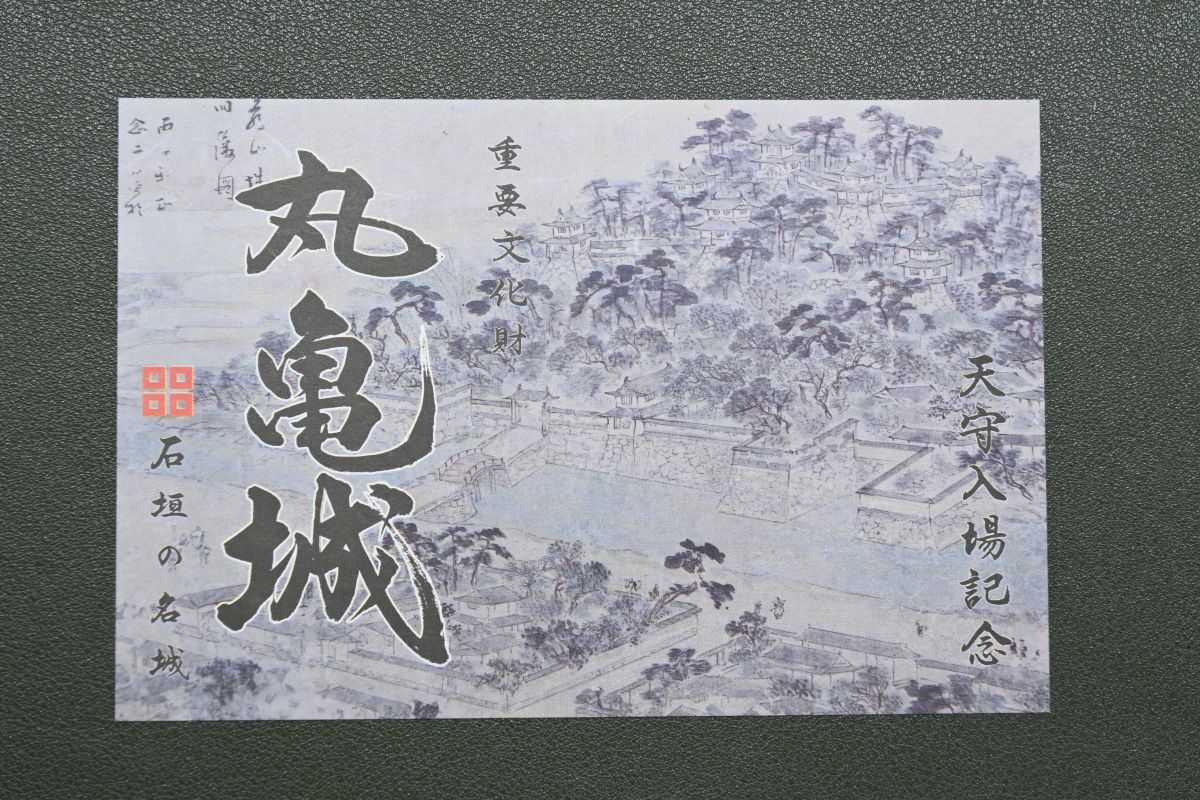
さいごに
小さいながらも、旧国宝に指定されていただけあって、その迫力は凄みがあった。
順調にいけば5年後に復元した石垣の姿が見れるはずなので、その時にもう一度来てみたい。


コメント